中学校の化学の授業で、青いガスバーナーの炎の中に銅線を差し出したところ、緑色の炎が上がった。炎色反応だ。それを見て同じ実験班で隣の席の華村 咲子は俺に「それ、どうしてそんなにも蒼いの?」とフリップに書いた文字を見せて寄越した。
当時中1だった俺はそれがガスバーナーの青い炎のことを言ってるのか、銅線を燃やして出た緑の炎について言ってるのか答えが分からなかったが、家に帰って辞書を調べると、蒼、とはどうやら緑に近い色合いのことを意味しているらしく華村の文学的なセンスに俺は唸った。
華村は口がきけない。心因性だか何だか分からないが、彼女は人に何かを伝えるときはスケッチブックに字を書いて説明をする。
彼女は人と話をしない分だけ熱心に本を読んでいた。中一にして銅線を燃した緑を蒼と評する感性も、本が育て上げたものだったのだろう。
華村はいつも1人だった。人と関わりを持つのが好きではないような雰囲気があったが、俺にはなぜかよく懐いていた。
華村と俺の家が近かったというのもあっただろうが、俺は俺で人と関わりあうのが好きではなくて、一人で黙々と化学の実験やら勉強をしているのが好きだったから、そういう互いに干渉しない気の遣わない感じが良かったのかも知れなかった。
あるいは俺は化学が好きで華村は文学が好きで、何かを極めようとするもの特有の空気だとか匂いだとか、そういったものを本能的に感じとっていたのかも知れなかった。
***
やがてお互いに高校生になり、俺たちはよく手話で会話をするようになった。
華村は文系へ俺は理系へ行ったことで以前ほどの関わりはなくなったが、それでも互いに気にかけてはいた。
あいつが文化祭で出していた作品には目を通して感想を送ったし、あいつからは俺が国際化学オリンピックの予選に出たときに激賞の言葉を短歌に乗せて送ってきた。
結局、その時は泣かず飛ばずに終わったが、その時の経験から俺は化学をもっと勉強しようと思った。
華村は華村で、俺に戯れに送った短歌がひとつのきっかけになっていた。華村は喋れない分文章で饒舌に語りたがる節があったが、それをたった30文字程度に落とし込む短歌という文化にのめり込んでいったようだった。
***
俺たちは大学へ進学してさらに関わり合いが減っていったが、それでも連絡は取り合っていた。
そんな中大学3年生になって、華村は喋れないという気後れから、就職をせずに小説家で食っていくつもりだ、と書いて寄越した。
「お前、プロになれんのか?」
「分からない。でも、やってみたいんだ」
文章から滲み出る静かな闘志の気配に俺は
「がんばれ」
とだけ送った。
***
華村はうまくいっていないようだった。
俺が化学メーカーに就職が決まった時、華村は相変わらず小説を書き続けていて、そして迷っているようだった。
「もうダメかも」
弱気な華村のメールに俺は喝を入れるべく、大学の研究室で撮った銅線をバーナーで炙った動画を送った。
「何色に見える?」
「ーー蒼?」
「その感性が残ってるなら、なにも問題はない。大丈夫だ」
華村はこのメールを見て、きっとハッとなったろう。
俺はあの日、あの時、華村の感性を見て、彼女を信じるようになったのだ。
その時の気持ちが生きているなら何も問題ない。
そして、華村は1本の小説を書いた。
やがてそれは文壇で話題になり、華村は新進気鋭の小説家として芥川賞を獲り、色々なメディアを横断していった。
その小説はというと、華村がここまでの自分の生き方のターニングポイントを短歌にして、それらを埋め込んだ自伝小説を書いたのだ。
物語は俺と華村が化学実験をする中学1年のあの頃から始まっていた。
その書き出しはこうだ。
『ーーそれ、どうしてそんなにも蒼いの?』
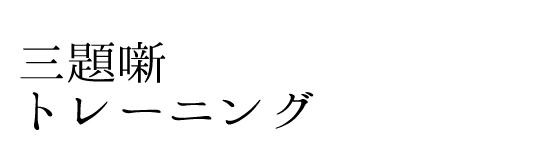


コメント
child porn
Thanks towards putting this up. It’s well done.
This is the compassionate of literature I rightly appreciate.
Alright, let’s check out 255betvip. Heard it’s a good spot for a little wagering. Let’s see if the rumors are true! Come and see by yourself there: 255betvip
Alright, checking out 515bet5. Heard mixed things, but I gave it a go. Site’s clean and mobile-friendly, which is a plus. Gameplay’s smooth. Worth a look if you need something new. See for yourself: 515bet5.
656bet1, eh? I’ve poked around. They’ve got a good selection of sports to bet on, and some decent bonuses. Nothing crazy, but worth checking out if you’re shopping around: 656bet1.